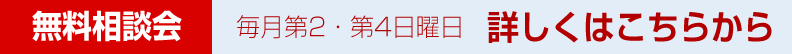Posted on 2月 25, 2022 - ニュース
本日特許庁HPにおいて、いわゆる「マルチマルチクレーム」が、日本国においても令和4年4月1日(新年度)から禁止されることがアナウンスされました。
どういうことかと言いますと、多少誇張した言い方になるかもしれませんが、極めて大雑把に言うと、今まで可能であった「発明の多面的保護」が出来なくなる(出来難くなる)ということになります。
新年度以降に特許出願や実用新案登録出願をされる方々にとっては、非常に大きな留意事項になりますので、今回、新着情報としてご紹介させて頂きたいと思います。
まず、「マルチマルチクレーム」とは何か、ということを説明させて頂きます。
特許出願や実用新案登録出願を行う際、出願人は複数の出願書類を作成する必要がありますが、その内の1つに【特許請求の範囲】(実用新案登録出願の場合には【実用新案登録請求の範囲】)という書類があります。
この【特許請求の範囲】は更に【請求項(クレーム)】という単位で構成されており、以下のような表現で記載されることが多いです。
【請求項1】Aを有することを特徴とする組成物。
【請求項2】Bをさらに有することを特徴とする請求項1に記載の組成物。
【請求項3】Cをさらに有することを特徴とする請求項1または請求項2に記載の組成物。
【請求項4】Dをさらに有することを特徴とする請求項1~請求項3のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項5】Eをさらに有することを特徴とする請求項1~請求項4のいずれか一項に記載の組成物。
ここで、【請求項1】のことを「独立項(メインクレーム)」と言います。
一方、【請求項2】~【請求項5】は自分よりも上位の請求項を引用している形式になりますので、このような請求項のことを「従属項」と言います。
そしてこの「従属項」については、更に、どの(いくつの)請求項にぶら下がっているのかによって、「シングルクレーム」、「マルチクレーム」、「マルチマルチクレーム」の3つに分類されることになります。
「シングルクレーム」は、引用先の請求項が1通りしかない請求項のことを言います。
上記例では【請求項2】が、引用先が1通り(請求項1)のみになりますので、「シングルクレーム」になります。
「マルチクレーム」は、引用先の請求項が複数存在する請求項のことを言います。
上記例では【請求項3~5】が、引用先の請求項が複数になりますので、「マルチクレーム」になります。
「マルチマルチクレーム」は、「マルチクレーム」の中でも、引用先の請求項に「マルチクレーム」の請求項が含まれている場合の請求項のことを言います。
上記例では【請求項4】と【請求項5】が、マルチクレームを含んでいることから、「マルチマルチクレーム」になります。請求項4は請求項3(マルチクレーム)を含んでおり、請求項5は請求項3(マルチクレーム)および請求項4(マルチクレーム)を含んでいます。
(なお、請求項3は引用先の請求項がメインクレームとシングルクレームですので、「マルチマルチクレーム」に対して「シングルマルチクレーム」と呼ばれることもあります。)
今回、この「マルチマルチクレーム」を記載することが禁止されることになりますが、「マルチマルチクレーム」が大変使い勝手が良い記載方法であることをイメージして頂くために、上記例をもう少し分かり易く、味噌汁を例にして書き直してみます。
【請求項1】豆腐を有することを特徴とする味噌汁。
【請求項2】ワカメをさらに有することを特徴とする請求項1に記載の味噌汁。
【請求項3】油揚げをさらに有することを特徴とする請求項1または請求項2に記載の味噌汁。
【請求項4】大根をさらに有することを特徴とする請求項1~請求項3のいずれか一項に記載の味噌汁。
【請求項5】ネギをさらに有することを特徴とする請求項1~請求項4のいずれか一項に記載の味噌汁。
さらに分かり易くするために、各請求項の内容(具材の組み合わせ)で書き直してみます。
(赤字・青字部分がマルチマルチに該当する部分になります。)
【請求項1】豆腐
【請求項2】豆腐+ワカメ
【請求項3】豆腐+油揚げ、豆腐+ワカメ+油揚げ
【請求項4】豆腐+大根、豆腐+ワカメ+大根、豆腐+油揚げ+大根、豆腐+ワカメ+油揚げ+大根(赤字部分が請求項3とマルチマルチの関係)
【請求項5】豆腐+ネギ、豆腐+ワカメ+ネギ、豆腐+油揚げ+ネギ、豆腐+ワカメ+油揚げ+ネギ、豆腐+大根+ネギ、豆腐+ワカメ+大根+ネギ、豆腐+油揚げ+大根+ネギ、豆腐+ワカメ+油揚げ+大根+ネギ(赤字部分が請求項3とマルチマルチの関係、青字部分が請求項4とマルチマルチの関係)
どうでしょうか。
請求項3(シングルマルチクレーム)までは組み合わせがそれ程は多くなりませんが、マルチマルチクレームとなる請求項4以降は組み合わせがぐっと増えて来るのがお分かり頂けると思います。
つまり、「マルチマルチクレーム」という記載形式は、請求項の最後の書き方を「請求項1~請求項●のいずれか一項に記載の…」という表現とするだけで、組み合わせを加速度的に増やすことができる記載形式なのです。
今まではこの記載形式がOKだったので、少ない請求項の数で(印紙代を節約しつつ)、且つ発明を多面的に表現することができたのですが、令和4年4月1日以降は認められなくなります。
マルチマルチクレームを認めてしまうと組み合わせが多岐に渡ることになり、審査の際に全ての組み合わせを洗い出してチェックしなければならず、審査に負担と時間がかかるというのが大きな理由です。
従って、令和4年4月1日以降は、印紙代を考慮しながら、従属項の書き方をどうするのか(どの請求項を引用先とするのか)を検討して出願することが非常に重要になってきます。
詳細は特許庁HPをご覧下さい。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/letter/multimultichecker.html